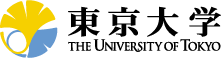第11回 発達保育実践政策学セミナー
- 日時
- 2016年3月9日 (水) 18:00〜20:00
- 場所
- 東京大学教育学部 第一会議室
- 講演
「胎児期・乳幼児期起源仮説の自然実験・介入実験による検証について:最近の経済学研究から」
澤田康幸(東京大学大学院経済学研究科)
澤田先生からは胎児期起源仮説へのミクロ経済学からのアプローチについて,お話しいただいた。研究手法についてのご説明,これまでの経済学で行われた胎児期起源仮説に関する知見の概観を踏まえ,先生の研究室で行われたインドでの実証研究をご紹介くださった。
ご発表の冒頭では,先生のご専門である実証ミクロ経済学の研究方法についてフィールド実験と自然実験を中心にご説明くださった。まず,実証ミクロ経済学で扱われるデータは,実験室実験から得られる統御されたデータと観察から得られる観察データがある。前者の実験室実験では,参加者が大学生で特殊で一部の人を扱ってきたため,そこから得られた結果の一般化や実社会での頑健性に疑問が残るという問題を指摘された。そこでより現実に近い設定で行われる人工型フィールド実験・枠組み型フィールド実験・自然フィールド実験の3つのフィールド実験の手法が紹介された。しかし,フィールド実験を行うことができない場合もあるといえよう。
そこで次に,今回の先生の研究室での胎児期期限仮説の実証にも用いられた自然実験という手法が紹介された。自然実験とは偶然や自然の振り分けをうまく利用し,実験条件への割り振りが近似的に行われた状態で研究を行う手法である。因果関係の識別においては「仮にその処遇を受けなかったらどうなっていたか」というセレクション・バイアス(その処遇から生じる効果以外の要因から生じる誤差のようなものと理解している)が問題となってくる。自然実験においてはセレクション・バイアスが0となっていると想定されるような偶然に注目し因果関係を識別しようとする手法であるという。
その後に,胎内での環境が後の子どもの成人病などの健康の帰結に結びつくという胎児期・乳幼児期起源仮説について行われてきた経済学研究の紹介と概観をしてくださった。経済学研究における胎児期起源説に関する研究の特徴として,大規模データを用いて自然実験を行うこと,健康問題のみを帰結として扱うのではなく,教育や所得といった社会的なものも帰結を扱うという特徴があるという。また途上国のデータを用いている場合も多いという。例の1つとして,アメリカのインフルエンザ流行期に生まれた人の教育水準が低く,低収入であることを示した研究が挙げられた。このような経済学における胎児期・乳幼児期起源説の実証研究の課題として特に,メカニズムの解明をすることができないということを強調されていた。
最後に先生の研究室で行われたインドにおける胎児期起源説仮説検証に関する研究がご紹介された。研究手法は自然実験であった。基準変数として子どもの身長・体重・BMI,死亡率といった健康指標だけでなく,児童労働やスクーリングもまた帰結となる変数として取られた。予測変数としては回顧法により,妊娠中の栄養状態・悲嘆・その他の思わしくない健康状態といった妊娠期の母体の健康状態がとられた。それ以外にも家庭の経済状況もまた予測変数として取られた。主な結果は,胎児期に母体の健康が思わしくないほど,後の子どもの身長が低くなること,そこには性差があったこと,児童労働が多くなりがちであること,通学が少なくなくなることを示すものであった。
参加者の声
質疑応答においては,胎児期起源説に経済学が取り組む背景,胎児期の環境の子どもへの(負ではない)正の影響の可能性,経済学から胎児期起源説に関する知見を実社会に応用する際に留意する必要のあるかについての議論があった。胎児期起源説の経済学的研究の背景としては,自然実験で扱いやすいという研究上の利便性と政策による介入可能性を広げるという2つの背景があるそうだ。次に,胎児期起源仮説が後の子どもへの負の影響を前提としていることが指摘され,正の影響は考えられないのか,その方向性で研究は行われないものか議論された。最後に,経済学研究から知見の実社会への応用について,2点の問題点が挙げられた。一つ目は外的妥当性,つまり一つの知見を他の場でも一般化できるか分からないという問題である。これについては,とにかくいろいろな国でやって知見を蓄積していくしかないとのことであった。2つ目の問題点は胎児期の母体の状態と後の子ども側の帰結の関連が明らかにされたとしても,メカニズムは解明されないということであった。メカニズムは一つ一つ仮説を立て,検証していくことで確かめていくという方法で解明していくとのことであった。
先生はご発表を通して胎児の時の母体の状態が後の子どもの帰結に結びつくということを示唆された。そこで特に興味深く感じたことは,健康上の帰結だけでなく教育・社会的な帰結にも結び付くということが大規模データから示されていたということであった。胎児期から子どもが成長するまで,そこにはかなりの個人差を生むだけの時間と子どもごとに異なった環境とのやりとりがあるということが想定される。また子どもの労働や学校に行くという行動は環境から大きく影響を受けるものであるように思う。そう思われるにも関わらず,胎児期の母体の健康状態が,それらを予測していたというのは興味深く,今後は,議論のなかで挙がっていたメカニズムの解明が期待される。それは介入を行う際にも重要になると思われる。なぜなら母体の健康状態,子どもの健康状態,児童労働や学校に行くということに共通して効いている変数がある可能性があり,介入の際には“母体の健康状態”の改善よりもその潜在している変数に取り組んでいくことが効果的であると思われるからである。これから行われるだろう多くの研究の契機としても胎児期の母体の状態と後の子ども側の帰結との関係を示すことができるという点からしても,自然実験を用いた胎児期起源説の経済学的なアプローチは興味深いものであった。
報告:小山悠里(東京大学院教育学研究科教育心理学コース修士課程)
「環境因子で刻まれる遺伝子の記憶:環境エピジェネテクス」
大迫誠一郎(東京大学大学院医学系研究科)
大迫先生からは、環境要因がDNA周辺にもたらす影響とその変化が生物の形質決定に与える影響についてご講演をいただいた。
本題に入る前に、大迫先生から生命科学の基礎知識についてレクチャーがあった。DNA分子が遺伝情報を担っていることは言うまでもないが、生物の形質はDNAのみによって決まるわけではない。生物にはエピジェネティクスと呼ばれる仕組みが備わっており、DNA周辺に化学修飾をすることによって個体発生後であってもDNAの発現を調節することができるのである。そして今日ではこの遺伝子における環境要因の部分の分子的な構造や機能がほぼ分かりつつある。それはヒトの発達に対しても重要な知見をもたらすだろうとのことだった。
最初に先生が引き合いに出していたのが、胎児期から出生後の発達期における環境因子が、成人後の健康や病気に影響を与えているというDOHaD仮説であった。これは先ほどの澤田先生の講演でもとりあげられたBarkerの胎児期起源仮説を拡張したものである。DOHaD仮説を裏付ける研究として、胎児期にBPAと呼ばれる環境ホルモンに曝露したマウスとそうでないマウスを比較すると、BPA曝露されたマウスでは黄色の個体が増加したという実験がある。BPAによって毛色を司る遺伝子の低メチル化(メチル化:特定のDNAの塩基配列にメチル基という物質を付加してその部位の遺伝子発現を不活性化すること)が行われたのである。
次に先生が話されたのは、ご自身の研究テーマでもあるダイオキシンと化学発癌についてであった。ダイオキシンは発がん性、催奇性などを持つ毒物であるが、ダイオキシン自体にDNA変化を引き起こす能力はない。つまりダイオキシンが人体に与える影響はエピジェネティックなものである可能性が高いということである。実際マウスに対して胎児期にダイオキシンを投与してから、発生60日後にベンツピレンという癌化を誘発する物質を投与すると、癌の発生率が高くなる。詳しく調べてみると、ダイオキシンを投与することによって、癌と関係しているCYP1A1プロモーターが低メチル化していたことが分かった。ダイオキシンによる癌の背景には、CYP1A1の低メチル化によってDNAの転写が促進され癌細胞が増えていくというメカニズムがあったのだ。
最後に先生が話されたテーマは環境因子による後世代への影響についてであった。獲得形質の遺伝ということについては既に19世紀に博物学者のラマルクが主張していたことではあったが、ダーウィンの進化論の登場によって否定されていた。それがエピジェネティクスの発見により近年また見直されつつあるのである。Anwayらによる研究によれば、ビンクロゾリンという環境ホルモンを妊娠中のラットに飲ませるとその息子や孫の世代まで精巣内の精子数が減少していたという。しかしこの分野の研究にはまだまだ信憑性が疑わしいものも多く、注意が必要であるという言葉をもって、講演を終えられた。
参加者の声
質疑応答では、iPS細胞におけるエピジェネティックな問題点、子供のストレスがエピジェネティクスに与える影響について、エピジェネティクスを使って良い方向にヒトの形質を変えることはできるのか? ヒトを対象にした他世代に渡る環境因子の研究例はあるか? など幅広い領域から様々な質問が飛び出した。前の講演者である澤田先生からは、ラットの実験を人間のレベルで見たときの、実証ミクロ経済学的な観点を基にした調査デザインについての発言もいただいた。私としても、ヒトの発達メカニズムが分子レベルで理解されるようになりつつある時代に改めて感動するとともに、ラットなどの動物で得られた知見を人間に対して適用する際の橋渡し的な研究ができたらと感じた。
報告:黒宮寛之(東京大学教育学部身体教育学コース4年)