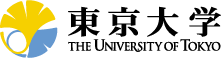- 日時
- 2016年4月20日 (水) 18:00〜20:00
- 場所
- 東京大学教育学部 赤門総合研究棟A210
- 講演
「乳児保育の質に関する研究の動向と展望」
野澤祥子(東京大学大学院教育学研究科)
野澤先生からは、乳児保育の質、中でも保育者と子どもたちの相互作用の質に焦点を当てて、子どもの自己主張の発達過程に関するご自身の研究も踏まえ、研究動向と展望についてご発表いただいた。
はじめに、乳児保育(3歳未満児の保育)について現状と課題をご説明いただいた。待機児童数が際立って多い年齢でもあり、多様な保育形態がある中では質のばらつきも大きく、十分に保障されているとはいえない。この現状で、改めて保育者と子どもとの関係について検討する必要があるとの問題提起であった。
次に、保育者と子どもの関係に関する研究についてレビューをしながら重要な点や課題についてご説明くださった。乳児保育では個別的で丁寧な関わりを通じて保育者・子ども間に安定した関係性を築くことが必要とされる。しかし、複数の子どもが存在する乳児保育においては難しさが伴う。子どもの自己主張の発達過程のパターンを扱った野澤先生ご自身の研究でも、保育者と子どもの人数比という量的側面だけではなく、集団の中で保育者とある子どもとの関わりが、他の子どもと保育者との関わりに影響を及ぼすという重要な点があるとのことである。子どもの潜在的なニーズに敏感に応答する保育者の専門性が求められる。
保育者と子どもの関係は、認知的・社会情緒的発達にも関係し長期的な影響が示唆されている他、低年齢児期の保育者との関係がその後の他の保育者や教師との関係に影響することもご紹介いただいた。ここで一つポイントとなるのが「集団的敏感性」の概念である。これは集団全体に目を配りながら子どもの個別性に敏感に応答するものであり、一対一のかかわりの中での「二者関係的敏感性」とは異なるが、アタッチメントの安定性と関連するものである。集団的敏感性とアタッチメントとの関連は、グループサイズや子どもと大人の比率によって変化しないという研究もある一方で、子どもの年齢による違いもあり、特に1歳前半の複数の子どもに対するかかわりの難しさが指摘される。
これらを踏まえて、近年開発されている集団レベルで保育者と子どものかかわりを評価する尺度(CLASS TODDLER)についてもご紹介いただいた。また、2か園における観察から、同じ「受容」であっても周囲の世界に開かれた「受容」が大切であることも示唆されている。すなわち、子どもと大人の二者関係に没入することで他の子どもを見失うことのないようにすることだけでなく、周囲の世界に開かれていることがその時にかかわっている子どもの発達にとっても重要である可能性が示唆される。
最後にまとめと課題として、今後は尺度を用いて保育者と子どものかかわりの質の評価・向上を目指すとともに、適切な比率やグループサイズ、かかわりの内実をより詳細に検討していく必要があるとのことである。二者関係は重要だが保育者個人のスキルのみに帰すのではなく、担当や集団の区切り方などにも様々な工夫が求められてくる。
参加者の声
質疑では、保育者と子どもの人数比率について、基準を超えると保育者の人数が増え、比率として子ども一人あたりは増えることになるのではという点や、一人の保育者が班についている形なのかといった質問がなされた。これらに関して、現場では全体を見ながら調整が行われており、基準とされている指標で十分なのかという検討が必要であること、また同じ6人でも1人の対応が困難だと状況は異なるなど、人数が実証的に定められているとはいえないことを語ってくださった。また、CLASS TODDLERが他者評価なのかという質問に対し、研修で認定をもらった人が行うことも補足された。
さらに、日本では複数の保育者が役割分担しながら複数の子どもを保育してきた文化があり、集団に対して1人が関わる前提の海外の尺度とは異なる面もあるという意見も出された。これに関して、連携しながら「開かれた受容」のある日本のメリットがあり、意識、目の向け方、身体知、環境構成の仕方なども含め、日本の保育の発信をしていけると良いといったことを語っていただいた。
今回聞かせていただいたことは、保育所で育つ子どもたちの多くが経験する乳児期からの集団生活において大切にすべきことについて、改めて考えるきっかけとなった。アタッチメントは1対1の関係性で論じられることも多いが、集団の中で求められる、家庭とは異なる専門的なスキルについて、今後より検討していく必要性を感じた。
報告:辻谷真知子(東京大学院教育学研究科教職開発コース博士課程)
「乳児期の眠り:睡眠脳波研究からわかってきたこと」
佐治量哉(玉川大学脳科学研究所)
佐治先生からは、乳児期の睡眠について、(1)子どもの睡眠に関する疫学調査、(2)新生児期・乳児期の睡眠動態、(3)乳児の睡眠脳波分析からわかってきたこと、の3部構成でご講演をいただいた。
(1)子どもの睡眠に関する疫学調査
まず、我が国で行われてきた疫学調査の紹介と、その一次データの佐治先生ご自身による再分析結果の紹介をされ、
などについて示された。
また、乳児(1歳未満児)を対象とした睡眠の疫学調査はこれまで実施されていないことを指摘し、今後乳児の睡眠に関する全国的な疫学調査を行う必要があるとのご指摘をされた。
(2)新生児期・乳児期の睡眠動態
次に、新生児期・乳児期の睡眠動態の特徴について、
などを解説された。
(3)乳児の睡眠脳波分析からわかってきたこと
最後に、ご自身の研究として、乳児の睡眠脳波の分析結果を紹介された。未発表データも含まれることから具体的な内容については省略するが、乳児の睡眠脳波の性差についてなど、大変興味深い最新のデータをご紹介いただいた。
(4)質疑応答
質疑応答の時間でも活発な議論が展開された。特に、睡眠覚醒リズムに対する家庭環境の影響については、きょうだいの有無(出生順位)や親の仕事など、社会的同調因子が子どもの眠りの発達に大きく影響しているとの議論がなされた。また、眠りの個人差についても質問があり、大人も子どももその眠りにはかなりの個人差が存在するが、個人内のばらつきは小さいとのご説明があった。実践的に良い睡眠を得るには、メラトニンなどのホルモンのサーカディアン依存性(非睡眠依存性)を考えた上でも、朝の時間帯の生活をコントロールすることが重要であるとのお話しがあった。
参加者の声
ヒトは人生の約3分の1を眠って過ごすが、乳児は一日の6割以上の時間を睡眠に費やす。佐治先生のご講演は、ヒトの発達を考える上で欠かせない「眠り」について改めて考えさせられる機会となった。
冒頭の疫学調査については、佐治先生も講演後に仰っていた通り、睡眠時間の測定法(=親の想起による自己報告)に限界があり、そこには系統的なバイアスが存在している可能性がある。より良い測定法の確立は、今後乳児の睡眠に関する調査を実施する上でも重要であり、技術の進展とともに発展が期待される。
乳児の睡眠について考えるときに、系統発生及び個体発生の過程においての位置づけやそのダイナミクスは非常に興味深い。乳児の睡眠については、佐治先生のように実際に脳波などの生理指標を測定してみなければ分からないことも多く、その本質を理解するためには脳活動の分析は重要であろう。今回は白熱したご講演で時間切れとなった部分もあったが、佐治先生の今後のご研究の発展を強く期待させる内容であり、参加者も大いに刺激を受けたことと思われる。
報告:岸哲史(東京大学教育学部身体教育学コース助教)