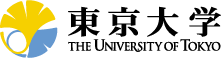- 日時
- 2016年9月7日 (水) 18:00〜20:00
- 場所
- 東京大学教育学部 赤門総合研究棟A210
- 講演
「幼稚園・保育所の普及とその地域差の両義性」
松島 のり子(福山市立大学教育学部)
松島先生からは、戦後日本の幼稚園と保育所の二元体制における全国の保育施設の普及状況の変遷とその地域差について、法令上の位置づけや統計データ、詳細な事例研究を交えてご講演いただいた(詳しくは、博士論文をまとめられた松島のり子著 (2015)『「保育」の戦後史――幼稚園・保育所の普及とその地域差』 六花出版をご参照いただきたい)。
本研究では、乳幼児に対する〈保育の機会〉に関わる従来からの課題である幼稚園・保育所の普及の地域差について、戦後(1945年~1980年)の国レベル・市町村レベルの実態や関連要因の歴史的変遷を丁寧に紐解くことで、〈保育の機会〉の地域差とは何かを改めて検討している。1947年に(学校教育法による)幼稚園と(児童福祉法による)保育所が制度化され、公的保育施設が日本社会に広く普及した。その後、幼保の二元体制のもと、1960年代には幼保の普及に著しい地域差が見られるようになり1990年代以降、少子化という国レベルの問題と同時に待機児童や過疎化といった問題が顕著になってきた。地域によって実情が異なる中で〈保育の機会〉の地域差はどのように形成され、対応されてきたのだろうか。
〈保育の機会〉の地域差について、本研究では2つの段階で捉えている。ひとつが、統計資料に示された幼稚園・保育所の普及推移にみられる地域差である。そして今ひとつが、各地域における幼稚園・保育所の設置に至る経緯に示される地域差である。幼保の普及推移を見てみると、地域によって「(幼稚園と幼稚園児数が顕著に増加する)幼稚園型」「(幼保が足並みをそろえるように増加する)幼保均衡型」「(幼稚園増加が停滞し、保育所が上回る)保育所後発型」「(幼稚園は緩やかに、保育所は顕著に増加する)保育所漸増型」そして「(戦後初期に保育所が急増する)保育所先行型」の5つに分類される。都道府県単位にとどまらず市町村単位の地域差が生じていることも、様々なデータに基づき可視化された。ここで取り上げた普及推移のデータは、都道府県や市町村、幼稚園と保育所の別という大きな枠組みでの量的側面の検討であったが、本研究ではさらに市町村レベルでそれぞれの普及推移をもたらした背景を詳細に分析していく。人口規模、都市/農村の別、公私の別や年齢別の普及の特徴が異なり歴史的経緯の比較検討に適しているとされた東京都の2区1市と石川県の2市1町の事例研究をしている。公私の調整が十分になされずどちらか一方が保育の機会を主に充たしてきた自治体や、公私間の調整を図るために首長の諮問機関を設置した自治体があり、さらに保育所と幼稚園の普及バランスや求められる役割も自治体によって異なっていた。事例分析を通して、地域の特性やニーズの違いとともに、自治体が果たしてきた役割の違いが示され、自治体間の歴史的変遷を比較する意義が示されていた。
最後に〈保育の機会〉について、松島先生は〈保育の機会の保障に関わって是正を要する地域差〉と〈多様に保育の機会を普及し、子どもに必要な保育を充たす可能性をもつ地域差〉の両義性がある、と考察されている。地域差が是正すべき課題として捉えられると同時に、地域の裁量によって柔軟に保育施設を普及してきた結果によるものであり、積極的な側面も見出すことができるという。本研究は幼保二元化体制であった1945年から1980年までの変遷に関する分析であったが、今後はすべての乳幼児の育ちを支える教育的かつ福祉的営みとしての「保育」の機会を、家庭環境や親の就労の条件にかかわらず多様な子どもの実態に応じて普く保育の機会を保障するために、制度や政策のあり方について問い続けていきたいとの言葉で締めくくられた。
質疑応答では、昨年4月に施行された子ども子育て支援新制度では市町村が実施主体となったが、本研究で示された地域差との関連をどう見るかという質問があった。松島先生からは、新制度では本研究でポジティブな側面として取り上げたような地域ごとにきめ細やかな対応ができる一方で、実態が多様で複雑であること、大きな制度的枠組みと地域の実情や政策がうまく繋がっていないように思うため、その部分を考える必要があると思うとのお答えがあった。また、本研究の地域差について行財政的側面も影響しているのではないかという問いに対しては、その通りで本研究では対象とできていないこと、また財政的側面に関しては首長の判断や議会の力が大きいと考えられること、また「財政的に厳しい」という主張はありうるが、保育や教育を後回しにして投資しなくてよいということではなく、安易に時もあるのではないかと指摘されていた。今後は、財政的側面や政治的側面も考慮に入れて分析していきたいと展望を語ってくださった。
参加者の声
国や都道府県レベルの分析だけでなく、基礎自治体レベルの実情に応じた保育施設の普及推移やその背景、そこから見えてくる自治体の取り組みの相違を丁寧に事例分析されていて、大変興味深く拝聴しました。特に、地域の特性やニーズに対して自治体が果たしてきた役割がそれぞれに異なっていたことが事例の比較によってわかりやすく示されていて、現在の子ども子育て支援新制度で懸念されている地域差や地域独自の先進的取り組み等を考察する上でも示唆的であると感じました。各自治体の取り組みについて、松島先生の提示されていた〈保育の機会〉の地域差にみられる両義的側面のどちらに主眼を置いているのか、あるいは両方を重視しているかといった観点から捉え直してみることで、保育の量と質に対する自治体の姿勢が見えてくると思います。新制度施行前後の普及推移やその背景要因に関する分析も待たれるところですが、今回はそうした現在を対象とした研究にも繋がる大変貴重なお話をありがとうございました。
報告:淀川裕美(発達保育実践政策学センター特任講師)
「経済的地位の世代間連関と教育の役割:国際的研究動向と日本子どもパネル調査の現状」
赤林 英夫(慶應義塾大学経済学部)
赤林先生には近年の教育経済学の問題関心と国際的な研究動向を踏まえて、日本子どもパネル調査の概要とその分析結果の一部をご紹介いただいた。なお、日本子どもパネル調査の詳細については赤林英夫・直井道生・敷島千鶴編著(2016)『学力・心理・家庭環境の経済分析 全国小中学校の追跡調査から見えてきたもの』有斐閣を参照して下さい。
近年の教育経済学には、実験デザインや操作変数法などを用いて因果効果を推計することに関心を持つ研究と、国際比較データや長期パネルデータの分析によって因果関係の解明より事実発見を重視する研究が存在するという。前者では学校選択制度や教育バウチャーといった公教育政策の費用対効果を推計し、後者では世代間の所得格差と家庭や教育の関係を検討している。今回の報告で取り上げるのは後者の研究である。
国際的に世代間の経済格差が固定化する中で、家庭の所得格差が子どもの学力にどのような影響を与えるのかについて関心が集まっており、アングロサクソン諸国を中心に実証的な研究が蓄積されている。アメリカでは学力と非認知能力の階層別格差が固定化していること、そうした格差が性別・人種間より所得階層間でより深刻であることが明らかになっている。同様の傾向は国際比較によっても確認されている。例えば、オーストラリア・カナダ・イギリス・アメリカの4ヶ国比較では、世帯所得と国語能力・問題行動の間に相関関係があることが実証されている。
こうした研究動向を踏まえて、日本における家庭環境と子どもの学力や心理の関係を解明するために実施しているのが「日本子どもパネル調査(JCPS)」である。本調査は、日本家計パネル調査(JHPS)と慶應義塾大学家計パネル調査(KHPS)の付帯調査として2010年に開始された親子パネル調査である。小学1年生から中学3年生までの子どもとその親を対象とし、その調査対象をほぼ2年に1度、継続的に追跡している。子どもの学力(認知能力)や非認知能力(問題行動・生活の質)などを測定するための調査項目を採用し、JHPSとKHPSで収集された世帯所得・親の学歴・家族構成などの豊富なデータも利用できる。そのため、家庭の経済格差と子どもの教育格差の関係を検討する上で妥当なデータであると言える。
本調査データの分析結果の一部を紹介する。第一に、クロスセクションデータの分析から世帯所得と子どもの学力の間に正の相関関係があることが明らかになった。特に、こうした効果は小学校高学年と中学生で顕著であった。第二に、子どもの学力水準のモビリティは小学校低学年より小学校高学年で低下していた。すなわち、小学校低学年と比べて小学校高学年では、学力の低い子どもが2年後に学力の上位グループに入るといった変化が起きにくく、学力格差の固定化が進んでいる。第三に、世帯所得は子どもの非認知能力とも関係している。クロスセクションデータの分析によると、世帯所得が高いほど子どもの問題行動は減少し生活の質が高まる傾向にある。これらの分析結果は他国でも共通して見られるという。
以上のように、赤林先生はJCPSを通じて教育の社会科学的な研究を活性化するともに、日本を国際比較の対象とするために必要なデータ整備を進めている。本調査のミクロデータは、慶應義塾大学パネルデータ設計・解析センターのウェブサイトを通じて、順次研究者に利用可能にされるとのことである。
参加者の声
世帯所得が子どもの学力や非認知能力に影響を与えるという実証的な結果は、社会にとって悲観的な意味を持つのかもしれない。近年の経済学では、優れた非認知能力を持つ子どもが将来高い所得を得る傾向にあることが知られているので、貧しい家庭に生まれた子供が貧しいまま大人になり自分の子供を産むという貧困の連鎖が想起される。そこで、今後の研究では世帯所得の低い家庭の子どもがどのような支援を受ければ、高い学力や非認知能力を身に付けることができるのかを明らかにする必要があるだろう。
報告:関智弘(発達保育実践政策学センター特任助教)