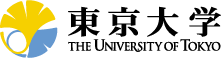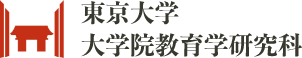科研費基盤研究(S)
「保育の質と子どもの発達に関する縦断的研究―質の保障・向上システムの構築に向けて」
日本学術振興会・科学研究費補助金による基盤研究(S)研究課題「保育の質と子どもの発達に関する縦断的研究―質の保障・向上システムの構築に向けて」(令和元年度〜令和5年)を実施します(研究代表者:野澤 祥子)。
研究の目的
乳幼児期に経験する保育の質が生涯の心理社会的適応や幸福に影響することが、欧米を中心に行われてきた長期縦断研究により実証され、乳幼児期の保育が世界各国で政策上の優先課題とされています。わが国でも保育の量的拡大が急激に進行し、幼児教育・保育無償化などの新しい政策が施行される中、保育の質の実態と子どもの発達への影響過程を的確に把捉し、質の保障・向上を支援するシステムを構築することが喫緊の課題となっています。
本研究では、第一に、保育の質を多面的に評価し、その実態を把握するとともに、保育の質が子どもの発達に影響する過程を縦断研究によって詳細に検討します。第二に、保育の質の保障・向上に向けた自治体の取り組みの実態を調査します。第三に、上記の調査結果に基づき、自治体と園の効果的取り組みのあり方を構想し、実装します。
以上の研究を通じて、保育の質の保障・向上を支援するシステムの構築に向け、多層的・多面的な知見を得ることを目的とします。
研究の方法
研究Ⅰ:保育の質が子どもの発達やストレスに与える影響過程の検討
保育の質と子どもの発達との関連について、0歳児クラスからの追跡調査を行います。調査開始に当たっては、研究協力者への説明と依頼を丁寧に進めます。
保育の「構造の質」に関しては、従来から検討されている保育者と子どもの比率等に加え、独自に開発した環境センシングシステムを保育室に設置し、温度・湿度・CO2濃度・騒音等の居住環境を調査します。「過程の質」に関しては、国際的な保育の質評価ツールに加え、独自に開発した日本の保育の質評価ツールを用います。さらに保育者の子どもへのかかわりは、情緒的利用可能性(emotional availability)という観点から評価します。
研究Ⅱ:保育の質の保障・向上に向けた自治体の取り組みの把握
自治体担当者とその自治体内の園関係者に対して、取り組みやその実施経緯、直面した課題等についてヒアリング調査を行います。また、全国すべての基礎自治体を対象として、子育て・保育に関する取り組みについての質問紙調査を実施し、全国的な実態の把握を行います。
研究Ⅲ:保育の質の保障・向上に向けた取り組みの構想及び実装
上記の研究の知見に基づいて、保育の質の保障・向上に向けた効果的な取り組みを構想し、その一部を自治体・園との協働で実施します。
期待される成果と意義
本研究では、保育の質と子どもの発達との関連を縦断的に検討します。その際に、保育の質に関して従来検討されてきた点に加えて、環境センシングや日本の保育の質評価ツールを用いることで、独自性の高いデータが得られると考えています。また、質の保障・向上において重要な役割を果たすと考えられる自治体の取り組みについても詳細に検討します。このように多層的・多面的な知見を得ることにより、保育の質の保障・向上を支援するシステムの構築に寄与したいと考えています。
調査実績
2019年度
園調査
・0歳児クラス予備調査
自治体調査
・保育の質の確保・向上の取り組みに関するヒアリング調査
2020年度
園調査
・新型コロナウイルス感染症流行に伴う乳幼児の成育環境の変化に関する緊急調査(保護者調査/保育・幼児教育施設調査)
・保育・幼児教育施設における新型コロナウイルス感染症に関わる対応や影響に関する調査(2020年度調査)
・0歳児クラス調査
自治体調査
・保育の質の確保・向上の取り組みに関する全国自治体調査
2021年度
園調査
・保育・幼児教育施設における新型コロナウイルス感染症に関わる対応や影響に関する調査(2021年度調査)
・保育・幼児教育施設長の新型コロナウイルス感染症への対応に関する縦断調査
・1歳児クラス調査
2022年度
・保育・幼児教育施設における新型コロナウイルス感染症に関わる対応や影響に関する調査(2022年度調査)
・2歳児クラス調査
2023年度
・3歳児クラス調査
調査報告実績
論文
野澤祥子・遠藤利彦・秋田喜代美 2023
保育・幼児教育施設における新型コロナウイルス感染症に関わる対応や影響についての検討(3)―クライシス・リーダーシップという観点から―
東京大学大学院教育学研究科紀要, 62
野澤祥子・淀川裕美・中田麗子・菊岡里美・遠藤利彦・秋田喜代美 2022
保育・幼児教育施設における新型コロナウイルス感染症に関わる対応や影響についての検討(2) ー2020年度・2021年度の動向と調査結果からー
東京大学大学院教育学研究科紀要, 61, 331-351
研究成果>論文のページから閲覧・ダウンロード
野澤祥子・淀川裕美・菊岡里美・浅井幸子・遠藤利彦・秋田喜代美 2021
保育・幼児教育施設における新型コロナウイルス感染症に関わる対応や影響についての検討
東京大学大学院教育学研究科紀要, 60, 545-568
研究成果>論文のページから閲覧・ダウンロード
野澤祥子 2021
新型コロナウイルス感染症に関わる保育・幼児教育施設の対応や影響について
小児保健研究80(1), 15-18.
著書
Sachiko Nozawa and Midori Takahashi 2022
How parents and children spent time during pandemic?: Exploratory study of home activity patterns and parental mental health COVID-19 Japan.
In Schutter,S., Harring, D., & Bass L.E. (Eds.) Children, Youth and Time Sociological Studies of Children and Youth Vol.30 pp. 49-68.Emerald Publishing.
新保庄三・野澤祥子2020
自園で新型コロナウイルスの感染者が出たとき: 事例に学ぶ 保育園・幼稚園・こども園で すぐにすること・日頃から備えておくこと
ひとなる書房
学会発表
滝口圭子・野澤祥子・佐川早季子・小崎恭弘・香曽我部琢・松井剛太 2023
1歳児クラスにおける保育の質の探索的検討― 保育の環境と保育者のかかわりから ―
日本保育学会第76回大会
野澤祥子・滝口圭子・高橋翠・遠藤利彦・秋田喜代美 2023
1歳児クラスの子どもと保育者の関係性と発達との関連「保育の質と子どもの発達に関する縦断的研究」から
日本発達心理学会第34回大会
野澤祥子・佐川早季子・滝口圭子・松井剛太・遠藤利彦 2022
新型コロナウイルス感染症に関わる保育・幼児教育施設の対応や影響5-コロナ禍が保育にもたらした変化とは―
日本乳幼児教育学会第32回大会
滝口圭子・野澤祥子・淀川裕美・小崎恭弘・香曽我部琢・松井剛太・渡邊由恵 2022
0歳児クラスにおける保育の質の探索的検討―保育の環境と保育者のかかわりから―
日本保育学会第75回大会
淀川裕美・野澤祥子・高橋翠・佐川早季子・滝口圭子・香宗我部琢・渡邊由恵・遠藤利彦 2021
新型コロナウイルス感染症に関わる保育・幼児教育施設の対応や影響4―コロナ禍下の保育と子どもの様子に焦点をあてて―
日本乳幼児教育学会第31回大会
野澤祥子・淀川裕美・高橋翠・佐川早季子・香曽我部琢・滝口圭子・遠藤利彦・秋田喜代美 2021
新型コロナウイルス感染症に関わる保育・幼児教育施設の対応や影響3-コロナ禍下の園長のリーダーシップと園の取り組みに焦点をあてて―
日本乳幼児教育学会第31回大会
高橋翠・野澤祥子・遠藤利彦 2021
新型コロナによる緊急事態宣言下における園へのアクセスと保護者の精神的健康の関連
日本乳幼児教育学会第31回大会
淀川裕美・野澤祥子・遠藤利彦・秋田喜代美 2020
新型コロナウイルス感染症に関わる保育・幼児教育施設の対応や影響2 -withコロナ・afterコロナの保育に焦点をあてて-
日本乳幼児教育学会第30回大会
野澤祥子・淀川裕美・秋田喜代美 2020
新型コロナウイルス感染症に関わる保育・幼児教育施設の対応や影響1 -感染症対策と職員のストレスに焦点をあてて-
日本乳幼児教育学会第30回大会
学会シンポジウム
Sachiko Nozawa, Mikiko Tabu, Sachiko Asai 2023
An examination of the positive aspects of the impact of COVID-19 on ECEC practice in Japan: Reexamination and reconstruction of the way and meaning of practice
31st EECERA Conference Self-Organised Symposium
野澤祥子 2023
保育の質と子どもの発達との関連の検討:「保育の質と子どもの発達に関する縦断的研究」から
野澤祥子(企画・話題提供)香曽我部琢(司会)砂上史子(話題提供)遠藤利彦(指定討論)無藤隆(指定討論)
保育環境・家庭環境の質と子どもの発達について考える―実証研究の知見から―
日本保育学会第75回大会自主シンポジウム
野澤祥子 2022
保育の質をいかに実証的に研究するか?~園調査の概要、及び0歳児クラス・1歳児クラスに関する結果の報告から~
野澤祥子(企画・話題提供)淀川裕美(司会)小崎恭弘(話題提供)遠藤利彦(指定討論)増田まゆみ(指定討論)
「保育の質をいかに実証的に研究するか:「保育の質と子どもの発達に関する縦断研究」から論点と可能性について考える
日本保育学会第75回大会自主シンポジウム
高橋翠 2021
子どものマルチメディア環境の実態と課題:緊急事態宣言下での保護者調査、全国図書館調査から
大会委員会企画シンポジウム「デジタル機器使用が子どもの発達に及ぼす影響」
日本発達心理学会第32回大会
論考
野澤祥子 2023
子どもとデジタルのかかわり
保育の友, 71(5), 14-18.
野澤祥子 2021
保育における価値の再発見:コロナ禍での経験を通して
東京都公立保育園研究会の広報 256, 4-5
野澤祥子 2021
子育てにおける夫婦の役割分担の再考―コロナ禍での調査をきっかけに考えたこと
家庭科, 5, 1-5.
野澤祥子・淀川裕美・高橋翠 2020
乳幼児とその施設への影響 東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター調査より
子ども白書2020, 50-53
招待講演
野澤祥子 2022
人権保育講座 タイムリー講座 保育の質の向上とコロナウイルス感染対策:2つの軸で園のあり方を考える
野澤祥子 2021
岐阜聖徳学園大学短期大学部岐阜保育研究会 第21回大会「コロナ禍の保育とコロナ後の保育の展望」
野澤祥子 2021
上越市私立保育園保育研究会 招待講演「ウイズコロナの保育」2021
野澤祥子 2021
令和2年度川崎市幼稚園協会研修大会 招待講演「コロナ禍の家庭環境と乳幼児~家庭と共に子どもの育ちを支えるには」2021
野澤祥子 2020
日本子どもの育成協議会 招待講演「ウィズコロナ・アフターコロナの保育」
野澤祥子 2020
金沢市社会福祉協議会 招待講演「ウィズコロナ・アフターコロナの保育環境」2020
淀川裕美・佐川早季子・箕輪潤子 2020
全国認定こども園協会 想いを受け取り対話で紡ぐ研修会「HoiQについて」
野澤祥子 2020
HITOWAキッズライフ株式会社乳幼児教育研究所 招待講演「『自園で新型コロナウイルスの感染者が出たとき』オンラインセミナー」
野澤祥子 2020
令和2年度日本保育協会青年部WEBセミナー「withコロナ・afterコロナの保育」
リーフレット
コロナ禍における園のクライシス・リーダーシップ:保育・幼児教育施設における新型コロナウイルス感染症に関わる対応や影響に関する調査結果(2020年度・2021年度)概要
国際シンポジウム
国際シンポジウム「日本とシンガポールの保育·幼児教育における新型コロナウィルスの影響」シンガポール社会科学大学
定例会議実績(オンライン実施)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 2020年6月30日 | 2021年4月20日 | 2022年4月19日 | 2023年4月11日 |
| 2020年9月15日・16日 | 2021年6月23日 | 2022年5月20日 | 2023年6月9日 |
| 2021年2月22日 | 2021年7月22日 | 2022年6月16日 | 2023年7月14日 |
| 2021年8月23日 | 2022年7月15日 | 2023年11月13日 | |
| 2021年10月12日 | 2022年8月19日 | ||
| 2021年12月14日 | 2022年9月16日 | ||
| 2022年1月11日 | 2022年10月28日 | ||
| 2022年2月14日 | 2022年11月25日 | ||
| 2022年3月8日 | 2022年12月26日 | ||
| 2023年1月27日 | |||
| 2023年2月27日 |